写真は当社製マフラーの集合部です。
以前はマフラーのエキゾーストパイプから作って
それに合わせて集合部を作っていたのですが
先に集合部を作って、
必要があればそれを加工して使用する
方法に変更しました。
今回すでに注文をいただいている分と
販売車両につける分などです。

写真では違いが解りにくいですが
集合部はとても大切な部品で、
作り分けています。
写真左からカワサキZ系、J系の鍛造ピストン、
スズキカタナ1100などのエキゾーストパイプが
42.7mm用。
その隣が41mmのGPZ900R(ニンジャ)系と
スズキ空冷750ccのボアアップ車、
(Z系、J系のエンジンノーマル車にも
使用する予定)
一番右が油冷GSX‐R750、GSXR-1100系の
38.1mm用です。
スプリングフックはまだついていない状態です。
CB750F、1100F系は集合部の形状が
特殊なため含まれていません。
元々当社製のマフラーは
一台一台現車に合わせて作るので
取り付け取り外しがしやすいのですが、
当社のお客さんは遠方の方が多いため
この製作方法で、より誰でも
オイル交換時に取り外し取り付け作業が
しやすいようになります。
ただ、差し込み部分にはカーボンが
付着しますから、それによってパイプが
抜きにくくなるのは仕方がないのですが。
少し前から、サイレンサーも変更しました。
またエンブレムも同デザインですが
変更し、現在製作中です。
これには一つの理由だけでなく
いろんな理由があるのですが、
立ちごけする方が意外と多く
サイレンサー単体の修理や交換などが
しやすいように、というのも
その理由の一つです。
逆に生産を辞めたのはショート管と
メガホンマフラーです。
こちらについてはすでにご注文いただいて
いる分は製作しますのでご心配なく。
先日Z1のショート管を作り終え、
近日塗装します。
エンジンにとって、キャブレター、
マフラー、点火系はセットのものであり
どれか一つでも調子が悪いと
本来の調子を発揮できません。
この本来の調子というものが
意外と解らないもので、
それはプロであるはずのバイク屋さんでも
解っていない方が多いですね。
だから平気で本来の調子で走らないものを
売っていたりする。
調子悪いなら悪いと言ってその分安かったり
すればいいのですが、
そんな店はほとんどないと思います。
何でも整備済み、調子いいです!
ですから。
それもそのはず、
取り扱い車種でないバイクについては
私も解らないものがあるのですから
他店でも同様のことがあって当たり前です。
解らない物は解るように
経験を時間とお金をかけて
積まなくてはなりません。
それが売る側の責任だと思います。
その経験を得るにはエンジンを
全てばらしてフルーオーバーホール、
車体側もきちんと整備して
点火系、マフラー、キャブも口径の
あったものでセッティングを施し
実際に走ってみることですね。
古いバイクにそれ以外方法がありますかね。
それを知っていれば、今売ろうとしている
古いバイクには何を整備しなければいけないかが
解りますね。
ただし、販売価格でどこまで整備、レストア、
チューニングできるかは変わります。
安い価格なのに、高いものと同じには
なりませんのでご注意を。
その金額の中でできるだけまともなものを
売るのが店側の良心だと思います。
得意な車種やエンジンであれば経験から
詳しく知っているので
本調子かどうかはすぐに解ります。
また同じエンジンでもチューニングの
度合いでもどれぐらい走るかを把握しています。
カワサキZ系ならノーマルのピストンで
750、900、1000、1100、
鍛造ピストンであれば
主に約1000~1200cc、さらにハイカム
が入ったもの、ポート加工されたもの
の違いなど、それぞれどれぐらい走るかを
把握しています。
他の車種はカワサキ車ほどの
チューニングは出来ないものが
殆どなので、そこまで幅はありませんが
それでもエンジンの仕様やマフラー、
キャブによって違いが結構あります。
例えばZ系にCRの29mm、31mmは
セッティングがあえば良く走りますが、
同じような排気量でも他社種の4バルブ
ヘッドのものにはFCRでもっと口径の
大きめの方が合っています。
CRの口径が大きいものはセッティングが
難しく、アクセルが重たいですね。
ひどいものはノーマルより走らない物を
平気で組み合わせて売っていたりします。
そんな時はバイクにとって(オーナーさんにも)
良い組み合わせなどではなく
自社の持っていた部品をただつけた、
あるいは仕入れ時についていた部品が
あっていないにもかかわらず
そのまま付けているなんてことが多いですね。
そりゃまともに走るわけがない。
自社でゼロから手を加えている
ショップさんは、パーツも自社の好みの
物を付けてまとめます。
だからある程度方向性がまとまって
自社らしいバイクになるわけです。
それが何の考えもなく、
ただ持っていた部品をつけたものであったり、
元々方向性の違うモノを使って
そのまま売っていてはまともに
走るわけはないですね。
その中でマフラーを自分自身で作っていると
良く解るのはこの部品の大切さです。
どのマフラーも同じようにパイプをつなぎ
作られているのに、
乗ってみると著しく走らないものがあります。
また良いマフラーなのにセッティングが
まるであっていなかったり
セッティングはあっているのに
キャブレター本体や点火系に不具合があって
中回転域で大きく引っ掛かりがあったり
することもあります。
マフラーの特性には作り手の好みがあります。
また沢山数を売るマフラーメーカーでは
徹底的に生産性が求められ、
それぞれ一台一台に合わせて作るなんて
ことは出来ません。
その中でも一般に売られている
まともなマフラーには共通するものがあって
ある程度抜けよく、音が不快ではなく、
セッティングに幅があるということです。
これは調整が少しずれても
走ることができるということです。
また手作りのものには見た目、音、
運転しても味のようなものがあります。
使用される材料にも一般で売られていない
物が使われていたり、生産の効率も
あまりよくないので価格は高め、
機械で多く作られ単純化されたものには
溶接やパイプの均一感があり
見た目は味気ないですが価格は安いですね。
ちなみに当社では他社さんのマフラーを
使う時も平気で加工します。
少しの事でグッと良くなることがあるからで
これは加工と言ってもセッティングみたいなもんです。
もちろんすごく安いのに何もしなくても
良いものもあります。
これはパイプサイズなんかで
少々調子悪くても走るようにできていますね。
ただエンジンに手を加えた時は
役不足になります。
当社のマフラーは
お客様が北海道から沖縄までおられるので、
結局セッティングの狂いが生じにくい物、
そういう物になってきました。
普段乗っているバイクについてる
マフラーがいまいちな時、
人は意外と気が付きません。
ですが今乗られているバイクについている
マフラーが良いものであったとき、
逆に悪いマフラーに付け替えてみれば
誰が乗ってもすぐに解ります。
要は知っているかいないかです。
せっかく気に入ったバイクに乗れているのなら
そういう部分にもこだわってみるのも
良いのではないでしょうか。


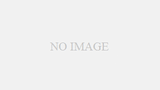
コメント